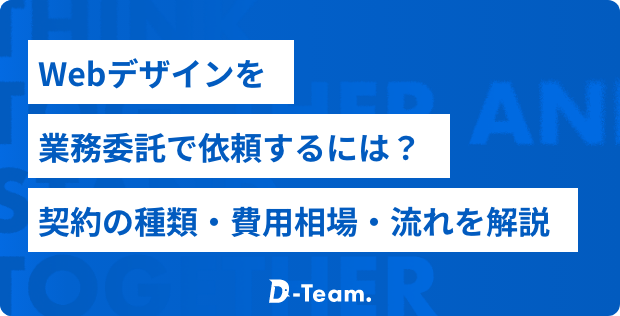
Webデザインを業務委託で依頼するには?契約の種類・費用相場・流れを解説
自社サイトの品質を高めたい、ブランドイメージを整理したい、リソース不足を補いたいといった課題に対して、Webデザインを外部へ業務委託する解決策が有効です。専門スキルを持つデザイナーや制作会社と連携することで、社内の負担を抑えながら高品質なデザインを実現できます。
一方で、業務委託には請負契約・委任契約・準委任契約など複数の形態があり、内容を理解せずに契約を進めると、成果や責任範囲が曖昧になってしまうこともあります。
この記事では、Webデザインを業務委託する際に押さえておきたい契約の種類や費用相場、依頼から運用までの流れを整理し、継続的に成果を上げるためのポイントを解説します。
Webデザインの業務委託とは?契約の種類を解説
Webデザインの業務委託とは、自社の社員ではない外部のデザイナーや制作会社に業務を任せる契約形態を指します。依頼内容に応じて、契約の種類は主に以下の3つに分類されます。
- 請負契約:成果物の納品を目的とする契約
- 委任契約/準委任契約:作業そのものや業務遂行を目的とする契約
Webサイト制作のように完成物を明確に定義できる場合は請負契約が多く、一方で運用・改善など継続的な支援を必要とする場合は準委任契約が選ばれます。契約の違いを理解することは、トラブル防止だけでなく、成果を最大化するためにも重要です。
請負契約・委任契約・準委任契約の違い
| 契約形態 | 主な目的 | 成果物の責任 | 契約終了の基準 |
| 請負契約 | 成果物の納品 | 受託者(制作側)が責任を負う | 成果物の納品・検収 |
| 委任契約 | 行為の遂行(専門業務など) | 受託者は善管注意義務のみ | 契約期間の満了 |
| 準委任契約 | 継続的な業務支援(開発・運用など) | 双方が協力しながら遂行 | 期間満了または終了合意 |
請負契約では、納品物の完成がゴールであり、納期や仕様を明確に定めるのが一般的です。一方、委任・準委任契約は成果ではなく、業務遂行に焦点を当て、タスク単位で柔軟に対応できます。
Webデザインでは、要件が流動的で継続的な改善が前提となるため、準委任契約が選ばれるケースが多く見られます。
Webデザインで準委任契約が選ばれる理由は柔軟性と継続性
Webデザインは、納品して終わりではなく、公開後の分析・改善を繰り返して成果を高めていくプロセス型の業務です。そのため、発注側と制作側が協力しながら、都度方向性を調整できる柔軟な契約形態が求められます。
準委任契約を選ぶ主なメリットは以下の通りです。
- 仕様変更への柔軟対応:途中で要件が変わっても調整しやすい
- 継続的な改善体制:アクセス解析やA/Bテストを踏まえて運用改善を行える
- 長期的な関係構築:デザインの一貫性やブランド理解を維持しやすい
一方で、成果保証がない点には注意が必要です。契約時に稼働時間・KPI共有・成果報告などを明確に設定しておくことで、透明性の高い協業が実現します。
Webデザインを業務委託するメリット
Webデザインの業務委託には、単なる制作コストの削減以上の利点があります。専門性の高いチームと継続的に協働することで、社内の負担を抑えながら、デザインの質とスピードの両立が可能です。ここでは、企業が業務委託を選ぶ主な理由を解説します。
専門スキルを持つチームに継続的に依頼できる
Webデザインには、UI/UX・マーケティング理解・コーディング知識など多岐にわたる専門スキルが必要です。業務委託を活用すれば、こうしたスキルを備えたデザイナーやエンジニアに、継続的に依頼できます。社内で一人のデザイナーを採用して教育する場合と比べ、スキルの幅や即戦力の面で大きな優位があります。
また、制作会社や外部チームは複数の業界案件を経験しており、トレンドや他社事例に基づく提案が可能です。結果として、より洗練されたデザインや、ユーザー行動を意識したサイト構成など、成果につながる改善が期待できます。単発の発注では得られない、長期的なナレッジの蓄積と品質の安定が、継続依頼の最大のメリットです。
社内人材を増やさずにデザインリソースを確保できる
新たにデザイナーを採用・育成するには、採用コストや教育期間、固定人件費など、時間と費用の両面で負担が大きくなります。業務委託であれば、必要なタイミングで必要なスキルを持つ人材に業務を依頼できるため、リソースを柔軟に調整できます。
特に、短期的なリニューアル案件やキャンペーンサイト制作など、時期によって業務量が変動する場合に効果的です。繁忙期だけ外部リソースを活用し、落ち着いた時期には委託量を減らすなど、事業計画に合わせて最適なバランスを取れます。固定費を抑えながら、高い専門性を確保できる点は、経営効率の観点からも大きなメリットです。
改善や運用も含めた長期的な成果創出が可能になる
Webサイトの価値は、制作時点ではなく、公開後の運用フェーズで決まります。アクセス解析を通じてユーザー行動を把握し、デザインや導線を改善していくことが成果を伸ばすことにつながります。業務委託契約を継続的に結ぶことで、制作と運用を分離せず、一体的に取り組むことが可能です。
制作を担当したチームがそのまま改善フェーズにも関わることで、デザインの意図や構造を正確に理解したうえで修正ができ、スピードと精度が向上します。加えて、データ分析やユーザビリティ改善などの専門的な提案を受けられるため、単なる制作依頼ではなく、成果をともに生み出し、事業成長に直結する長期的な成果を得やすくなります。
Webデザインを業務委託するデメリット・注意点
Webデザインを業務委託することは、専門的なスキルを効率的に活用し、高品質な成果を得るうえで非常に有効です。しかし、契約内容や進行体制が不明確なまま進めてしまうと、期待した成果が得られなかったり、スケジュールやコストが想定以上に膨らんだりといった課題が生じることもあります。
ここでは、委託を検討する際に押さえておきたい注意点を整理します。
成果保証が難しく進行管理が求められる
準委任契約などの業務委託では、業務を遂行すること自体が契約の目的となり、成果物の完成や数値的な結果を保証するものではありません。
そのため、最終的なデザインや成果物のクオリティが期待と異なる場合でも、契約上は問題になりにくい特性があります。特に、制作側と発注側の間で成果基準や納品範囲を明確に定義していない場合、認識のずれが生じやすくなります。
このようなリスクを防ぐには、発注側にも一定の進行管理力が求められます。制作の各フェーズで中間レビューを行い、都度フィードバックを共有しましょう。
また、進行管理ツールを活用してタスクや進捗を可視化し、成果物を段階的に確認できる環境を整えておくと、方向性を早期に修正できます。任せっぱなしにしないことが、業務委託を成功させる上で重要です。
コミュニケーションの齟齬による方向性のズレが起こる
Webデザインのプロジェクトは、企業のブランド戦略や事業目的と密接に関わります。そのため、社内チームと外部制作チームの間で情報共有が不足すると、デザインの方向性やメッセージ性にズレが生じるリスクがあります。
特に、発注側が誰に・何を伝えたいのかを十分に整理しないまま依頼を進めると、デザイン面では完成度が高くても、成果に結びつかないケースが見られます。
こうした齟齬を防ぐには、初期段階で目的・ターゲット・KPIなどを明文化し、共通認識を形成することが欠かせません。また、デザインレビューやミーティングの頻度をあらかじめ決めておき、都度の確認を通じて相互理解を深めましょう。
制作会社側のディレクターと自社担当者の役割分担を明確にし、意思決定のルートを一本化しておくことで、判断の遅れや修正の手戻りを防げます。プロジェクト全体を協働体制として捉える視点が成果の安定につながります。
著作権・データ管理の取り決めが必要になる
Webデザイン業務では、デザインデータやコーディングファイル、写真、イラストなど、多くの成果物が知的財産として扱われます。これらの著作権や利用権の取り扱いを曖昧にしたまま契約を進めると、納品後に再利用できない・一部データが納品されていないといったトラブルが起こることがあります。
契約書には、著作権の帰属先・利用可能な範囲・納品データの形式を具体的に記載しておきましょう。たとえば、納品後の修正や流用を社内で行えるか、別媒体への転用が可能かといった項目は、後の運用に大きく影響します。
また、継続的な委託契約では、運用フェーズで新たに作成されたバナー・画像・テキストなどの素材の著作権がどちらに帰属するかも明確にしておきましょう。
さらに、データ管理のセキュリティ面も軽視できません。クラウドツールの権限設定やファイル共有方法を事前に取り決め、プロジェクト終了後のデータ保管・削除ルールまで含めて整理しておくと安心です。
業務委託で依頼できるWebデザイン業務の範囲
Webデザインの業務委託ではデザイン制作にとどまらず、設計からブランドの印象を左右するビジュアル制作、公開後の運用・改善まで、幅広い業務を委託することが可能です。企業がどの段階に課題を抱えているかによって、依頼する内容や契約の形も変わります。
UI/UX設計でユーザー導線とサイト構造を最適化する
Webサイトの成果は、見た目の美しさだけでなく、どれだけユーザーが目的の情報にスムーズにたどり着けるかによって左右されます。UIやUXの設計は、訪問者の行動を分析し、サイト全体の導線や構造を最適化する工程です。
UI/UX設計では、情報設計やワイヤーフレームの作成、ユーザーテストの実施などが行われます。業務委託先のデザイナーやディレクターが、ユーザー視点とビジネス目的の両方を考慮しながら設計を進めることで、成果に直結する土台を作ります。
特に企業サイトやBtoBサービスのように、資料請求・問い合わせ・採用など複数の目的が存在する場合、UI/UX設計の質が成果を大きく左右します。
ビジュアルデザインやLP制作でブランドを強化する
UI/UX設計で定めた構造をもとに、具体的なデザイン表現を形にしていくのがビジュアルデザインの工程です。ここでは、企業のブランドイメージや事業メッセージを視覚的に伝える力が求められます。業務委託によって経験豊富なデザイナーに依頼すれば、トレンドを取り入れつつ、統一感のあるデザインを実現できます。
また、LP制作も代表的な委託業務の一つです。広告やキャンペーンと連動したLPは、短期間で成果を出すために重要であり、デザインだけでなく、コピーライティングや構成の最適化も含めて制作されます。
社内リソースだけで対応するのが難しい多面的な要素を、外部チームが専門的にカバーすることで、デザインの完成度とブランド訴求力が高まります。
運用・改善支援で公開後も継続的な成果向上を図る
Webサイトは公開してからがスタートです。アクセス解析やヒートマップなどのデータをもとに、ユーザー行動を分析し、デザインや導線を継続的に改善していくことが求められます。
制作を担当したチームがそのまま改善業務も担うことで、サイトの構造やデザイン意図を踏まえた効率的な対応が可能です。ページの改修やA/Bテスト、コンテンツ更新などを通じて、成果を定量的に検証しながら、長期的なパフォーマンス向上を実現します。
企業側は、定期的な報告やミーティングを通じて進行状況を把握でき、戦略的に運用を進められることが大きな利点です。
Webデザイン業務委託の費用相場は月20〜80万円が目安
Webデザインを外部に委託する際の費用は、担当範囲や関与する人材のスキルレベルによって大きく異なります。一般的には、月額で20万円から80万円が一つの目安です。
| 業務内容 | 想定月額費用 | 業務の特徴・依頼範囲 |
| UI/UX設計 | 25〜40万円 | サイト構造や導線設計、ワイヤーフレーム作成などの設計業務。改善フェーズでの活用も多い |
| Webデザインの新規制作 | 50〜60万円 | 新規サイトやLPのデザイン制作。ブランドイメージ構築やビジュアル開発が中心 |
| Webデザインのリニューアル | 60〜70万円 | 既存サイトの構成を活かしつつ、デザインの再構築と改善提案を行う中規模案件 |
| ECサイト構築・コーディング | 50〜65万円 | デザインデータをもとにHTML/CSS/JavaScriptで実装。機能連携やCMS対応が発生する場合もある |
金額はあくまで目安であり、契約内容によって変動します。継続的な運用支援を行う準委任契約では、作業範囲や稼働時間に応じて月額費用が設定されることが一般的です。
費用を検討する際には、単に金額を比較するのではなく、デザイン以外にどの業務が含まれているか、改善提案やレポート対応まで委託できるかといった点を確認しましょう。
Webデザインの業務委託・準委任契約が向いている企業・向かない企業
Webデザインの依頼方法は、目的や期間、求める成果の性質によって最適な契約形態が異なります。特に、継続的な改善を重視する企業と短期納品を求める企業とでは、適した契約モデルが大きく変わります。ここでは、それぞれの特徴をまとめました。
継続的なサイト改善や運用を重視する企業は業務委託・準委任契約
Webサイトを単なる広報媒体ではなく、継続的に成果を生み出すマーケティング基盤として運用したい企業には、業務委託、特に準委任契約が向いています。UI/UX改善やデザインのアップデートなど、運用フェーズを通じた改善活動を継続するには、柔軟にタスクを調整できる契約形態が適しています。
準委任契約では、期間を定めて一定の稼働時間内で業務を遂行するため、サイトの課題を分析しながら優先度をつけて対応することが可能です。
業務委託・準委任契約は、自社内に専門人材を抱えずに長期的な運用を行いたい企業や、複数部門が関わる大規模サイトを運営する企業にも適しています。
短期納品や単発制作を重視する企業は外注・請負契約
明確な納品物があり、期限までに成果物を完成させたい場合は、外注・請負契約のほうが適しています。新規キャンペーンサイトや期間限定のLP制作など、短期間で成果を求める案件では、納品範囲と仕様を明確に定義できる契約形態のほうがスムーズです。
請負契約では成果物の完成が契約の目的であるため、費用や納期を固定しやすく、社内のディレクションリソースが限られている場合にも進行しやすい利点があります。
ただし、納品後の運用や改善が別契約になることが多いため、継続的なサポートを前提とする場合は、別途体制を整える必要があります。
Webデザイン業務委託の進め方|契約から運用までの流れ
Webデザインを外部に委託する際は、目的の整理から契約、進行管理、運用フェーズまで、一連のプロセスを計画的に進めましょう。流れを理解しておくことで、依頼内容のズレや成果の不一致を防げます。
委託前に目的・範囲・KPIを明確化する
まずは、なぜWebデザインを委託するのかという目的を整理しましょう。新規サイトの立ち上げ、既存サイトの改善、運用体制の強化など目的によって、求めるスキルや契約形態が変わります。
同時に、業務範囲とKPIを明確に設定しましょう。たとえば、「CVRを◯%改善したい」「ブランドイメージを刷新したい」など、目指す成果を定義することで、委託先が具体的な提案をしやすくなります。要件を曖昧にしたまま進めると、後の見積もりや制作フェーズで齟齬が生じやすいため、社内で共通認識を持っておいてください。
見積もり・契約締結する
目的と範囲が明確になったら、次に見積もりの依頼と契約の締結に進みます。複数の制作会社やフリーランスに相見積もりを取り、費用だけでなく、対応体制やスケジュール、制作実績を比較検討しましょう。
契約書では、納品範囲・スケジュール・修正回数・著作権の扱いなどを具体的に定めて置きます。請負契約であれば成果物の完成基準を明確にし、準委任契約の場合は稼働時間や成果報告の方法を取り決めておくことでトラブルを防げます。
また、長期的な委託を前提とする場合は、初月をトライアル期間として設定し、相互の相性や進行フローを確認するのも有効です。
制作開始後は定例ミーティングと進行管理で品質を担保する
制作が始まったら、進行管理とコミュニケーションの体制を整えましょう。特にWebデザインは要件や方針が途中で変わることも多いため、週次や隔週など定期的なミーティングを設けることで、方向性のズレを早期に修正できます。
制作会社側のディレクターと、自社担当者の役割を明確にし、レビューのタイミングやフィードバック方法をルール化しておくと、作業効率が大幅に向上します。また、FigmaやNotion、Slackなどのツールを併用することで、進行状況や修正履歴を共有しやすくなり、品質を安定的に保てます。
運用フェーズでは改善提案と成果報告を継続する
サイト公開後は、運用フェーズとして継続的な改善を行う段階に移ります。アクセス解析やヒートマップなどのデータをもとにユーザー行動を可視化し、課題を特定したうえで改善施策を提案・実行します。
月次レポートや定例会を通じて、委託先から成果報告や改善提案を受ける仕組みを設けると効果的です。成果の検証を重ねながら、KPI達成度を確認し、次の施策に反映していくことで、委託関係が単なる制作依頼ではなく、ビジネスパートナーとして機能するようになります。
業務委託で継続的に成果を出すWebデザイン体制を構築しよう
Webデザインの業務委託は、長期的に成果を出し続けるために有効です。特に準委任契約のように柔軟な契約形態を選ぶと、発注側と制作側が協力しながら、状況に応じた改善や方向転換を行える体制を築くことが可能です。
サイト制作は作成して終わるものではなく、公開後の運用や分析を通じて、デザインを継続的に磨き上げていくことが求められます。このサイクルを無理なく回すためには、外部の専門チームと長期的に連携し、設計・制作・改善を一貫して進められる体制が欠かせません。
自社のリソースだけでは対応しきれない領域を外部と協働しながら補完し、継続的な成果を生み出せるWebデザイン体制を整えましょう。
一覧へ戻る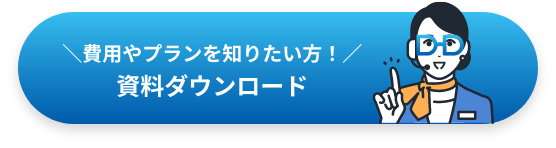 PAGE TOP
PAGE TOP