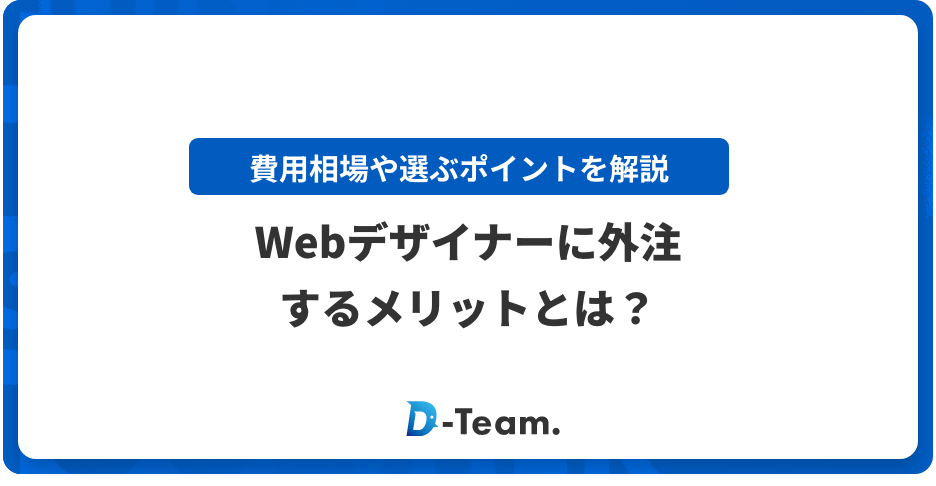
Webデザイナーに外注するメリットとは?費用相場や選ぶポイントを解説
「自社のWebサイトを作りたいけれど、社内にデザイナーがいない」「外注するとどのくらい費用がかかるの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。
Webデザイナーに外注することで、デザイン性と集客効果を両立したサイトを効率的に制作できます。さらに、社内の業務負担を軽減し、公開後の運用サポートも受けられるのが大きな魅力です。
この記事では、Webデザイナーに外注するメリットや依頼できる業務内容、費用相場、選び方のポイント、制作の流れまでをわかりやすく解説します。
これを読めば、初めて外注を検討している方でも、どのような流れで依頼すればいいのか、どれくらいの費用を見込むべきかが具体的にイメージできます。
Webデザイナーに外注するメリット
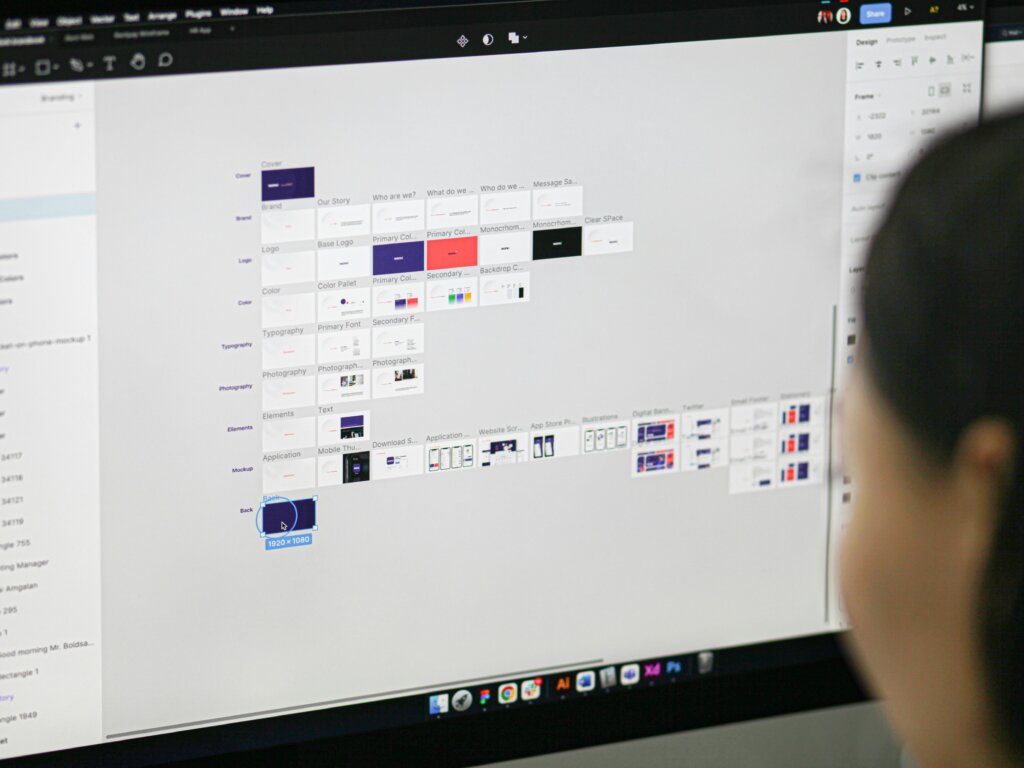
Webデザイナーに外注するメリットは、デザインとコンバージョンの両立ができる・社員が本来の仕事に集中できる・公開後のサポートを受けられることが挙げられます。
単なる制作代行にとどまらず、企業のWeb戦略全体を強化するうえで大きな役割を果たします。では、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
デザイン性の高さ・コンバージョンを両立できる
外注する一番の魅力は、デザイン性の良さとコンバージョンの出やすさを両立できる点です。プロのWebデザイナーは、さまざまな業界のサイトを手がけてきた経験があり、ユーザーがどのような行動をとるかをよく理解しています。そのため、単におしゃれなデザインにするだけでなく、訪問者がスムーズに目的を達成できるような導線づくりが得意です。
また、スマホ対応やSEOを意識した構成など、最新のWebトレンドをしっかり取り入れるのも大きな強みです。自社で一から学びながら作るよりも、外注したほうが短期間で完成度の高いサイトを作れるでしょう。
社員が通常業務に集中できる
Webサイトの制作には、企画から素材づくり、修正対応まで多くの作業が発生します。社内スタッフだけで対応すると、他の業務に影響が出ることも少なくありません。外注を利用すれば、制作の手間をプロに任せられるため、社員は自分の仕事に集中できます。
さらに、デザイン担当者を新たに採用したり育成したりする必要もないので、人件費や時間のコストを抑えることが可能です。限られた人員で動いている中小企業にとっても、外注は効率的な選択といえます。
公開後の情報更新やドメイン・サーバー管理も教えてもらえる
Webデザイナーの中には、サイトを公開したあとに発生する業務についてアドバイスができる方もいます。例えば、情報を更新する方法のほか、ドメインやサーバーの設定・管理についてアドバイスを受けられます。セキュリティやSEO対策など、運用面のサポートを行うケースもあります。
特に初めて自社サイトを運営する場合、こうした知識はとても心強いものです。外注を通じて運用ノウハウを吸収し、自社でも少しずつメンテナンスできるようになると、長く安定してサイトを運営できます。
Webデザイナーに外注できる主な業務内容

Webデザイナーに外注できる業務は、単にデザインを作ることだけではありません。サイト全体のコンセプト作りから設計、デザイン制作、最終的なコーディングや公開まで、一連の工程をトータルで依頼できます。
ここでは、一般的に外注できる主な作業内容をご紹介します。
コンセプト・イメージ設計とすり合わせ
まず、サイトの方向性や目的を明確にするための打ち合わせを行います。ここでは「どのようなターゲットに向けたサイトにしたいのか」「どのような印象を与えたいのか」など、コンセプトやイメージをすり合わせていきます。
外部のデザイナーはヒアリングを通じて、企業の強みやブランドの特徴を整理し、それをビジュアルに反映する提案を行います。たとえば、信頼感を重視した企業サイトや、親しみやすいサービスサイトなど、目的に合った世界観を具体化します。
ワイヤーフレームの作成
ページの構成を可視化するワイヤーフレームを作成します。ワイヤーフレームは、Webサイトの設計図のようなもので、どの位置にメニューやボタン、画像、テキストを配置するかを決めていきます。
ワイヤーフレームの作成によって、情報の整理や導線の確認ができ、ユーザーにとって使いやすいレイアウトを検討することが可能です。デザイナーとコミュニケーションをとりながら、どのページで何を伝えるのか、どのような行動を促したいのかを明確にしていきます。
デザインの作成
ワイヤーフレームが完成すると、いよいよデザインの制作に入ります。色使いやフォント、写真やイラストなど、実際の見た目を決めていく工程です。
Webデザイナーは、ユーザーの心理や視線の流れを考えながら、見やすく印象に残るデザインを作ります。また、企業のブランドカラーやロゴを活かした統一感のあるデザイン提案を行うことも多く、見た目の美しさだけでなく、企業のイメージを効果的に伝えることが可能です。デザイン案は数パターン提示されることもあり、細かい修正を重ねながら完成形へと近づけていきます。
コーディングでの実装
デザインが完成したら、それを実際のWebページとして動かすためのコーディング作業に進みます。HTMLやCSS、JavaScriptなどのプログラミング言語を使って、ブラウザで正しく表示されるように実装します。
コーディングでは、見た目を再現するだけでなく、ページの表示速度やSEO対策にも関わる部分が多くあります。外注することで、最新の技術を取り入れた高品質なコードで実装できるのが大きなメリットです。スマホ・タブレットでも見やすく表示するレスポンシブ対応や、動作チェック、軽量化なども行われます。完成後はテストと修正を経て、正式に公開へと進みます。
Webデザイナーの外注先を見つける方法

Webデザイナーの外注先を見つける方法として代表的なのは、制作会社やデザイン会社に依頼する、クラウドソーシングを利用する、SNSやWeb検索から直接依頼する方法です。それぞれの探し方について、順に見ていきましょう。
Web制作会社やデザイン会社に依頼する
最も一般的で安心感のある方法は、Web制作会社やデザイン会社に依頼することです。制作会社にはデザイナーだけでなく、ディレクターやエンジニア、ライターなど複数の専門職が在籍しており、企画から設計、制作、公開までを一括で任せられます。
会社としての実績や体制が整っているため、クオリティの高いデザインと安定した進行管理が期待できます。打ち合わせを重ねることで、ブランドの方向性や目的に合ったデザイン提案を受けられる点も魅力です。料金はやや高めになる傾向がありますが、初めて外注する場合や大規模なサイトを作る場合には、もっとも失敗の少ない選択です。
クラウドソーシングサイトで募集する
コストを抑えながら柔軟に依頼したい場合は、クラウドソーシングを活用する方法があります。クラウドワークスやランサーズなどのサイトを利用すれば、登録しているフリーランスのWebデザイナーに直接募集をかけられます。
依頼内容や予算、納期などを掲載しておくと、それに合ったスキルを持つデザイナーから応募が集まります。ポートフォリオや過去の評価を確認しながら比較できるため、自社のイメージや予算に合う人材を見つけやすいのが特徴です。
ただし、個人に依頼する場合は、納期や修正対応、著作権の取り扱いなどを事前に明確にしておくことが大切です。やり取りを丁寧に進めることで、信頼関係を築きながらスムーズに制作を進められます。
SNSやWeb検索から探して直接依頼する
SNSを活用してWebデザイナーを探すことも可能です。たとえばX(旧Twitter)やInstagramなどでは、デザイナー自身が作品や制作実績を発信していることが多く、そこから気になる人に直接コンタクトを取れます。
SNS経由なら、ポートフォリオサイトや投稿内容からデザインの傾向や得意分野をつかみやすく、相性の良いデザイナーを見つけやすいのがメリットです。気になるデザイナーを見つけたら、メッセージで丁寧に問い合わせを行い、実績や納期、予算感などを確認してみましょう。
また、Google検索で「Webデザイナー 外注」「フリーランス Webデザイナー 東京」などのキーワードを使って探すのも有効です。検索経由では、地域や業種に特化したデザイナーを見つけやすい利点もあります。
Webデザイナーに外注する際の料金相場は1万円〜200万円以上

Webデザインを外注する際の費用は、どのようなサイトを作るか、ページ数や構成、依頼先のタイプなどによって大きく変わります。小規模なサイトであれば数十万円前後で収まることもありますが、ページ数が多い中〜大規模サイトになると、200万円を超えるケースもあります。
| サイト規模 | 費用の目安 | 内容の特徴 |
| 小規模 | 約30万円〜50万円 | 会社紹介や店舗サイトなど、5〜10ページ程度のシンプルな構成。テンプレートや既存デザインの活用が中心 |
| 中規模 | 約50万円〜200万円 | サービスページや採用ページなどを含む企業サイト。オリジナルデザインやSEO対応、CMS構築を行う場合が多い |
| 大規模 | 200万円以上 | ECサイトやポータルサイトなど、数十ページ規模の本格的な構成。システム連携や複数デバイス最適化が必要になる |
ページごとの制作単価も、内容やデザインの複雑さによって幅があります。以下は、一般的なページ構成ごとの費用目安です。
| ページの種類 | 1ページあたりの費用目安 | 内容の特徴 |
| トップページ | 約5万円〜13万円 | 最初に訪問者が目にするメインページ。デザイン性やブランドイメージが求められるため、最も費用がかかる傾向 |
| 下層ページ | 約2万円〜7万円 | 会社案内・サービス紹介・問い合わせページなど。構成がシンプルなため、比較的コストを抑えやすい |
| 派生ページ | 約1万円〜3万5,000円 | 下層ページのデザインを流用して作成するページ。更新頻度が高いコンテンツでよく使用される |
| ランディングページ(LP) | 約6万円〜20万円 | 広告やキャンペーン専用の1ページ完結型サイト。構成やコピー、デザイン要素が多く、費用に幅がある |
金額はあくまでも目安であり、実際の費用は制作内容やデザイナーのスキルによって前後します。また、修正対応の範囲や納品後のサポート、著作権やデータの扱いなども確認しておくと安心です。最初に条件を明確にしておくことで、想定外の追加費用を避けられます。
外注するWebデザイナーを選ぶ際にチェックするポイント

Webデザイナーを外注するときは、見積もりの金額だけで判断してしまうと、思ったような仕上がりにならないことがあります。大切なのは、デザイナーのスキルや対応の丁寧さ、自社との相性を見極めることです。ここでは、依頼先を選ぶ際に押さえておきたいポイントを順番に紹介します。
ポートフォリオで求めるデザインが可能であるか
まず確認したいのは、デザイナーのポートフォリオです。ポートフォリオを見ることで、デザインの傾向や得意分野、仕上がりのクオリティを具体的に把握できます。自社のイメージに合うデザインテイストを叶えられるかどうかを見極めましょう。
たとえば、スタイリッシュで洗練されたデザインを希望するのに、ナチュラルやポップ系を得意とするデザイナーに依頼すると、方向性がずれてしまう可能性があります。掲載されている作品の雰囲気が、自社ブランドや目的に近いかをチェックしておきましょう。
過去の制作実績が豊富であるか
実績の多さは、経験値の高さを示す一要素です。これまでどのような業界や規模のサイトを手がけてきたのかを確認することで、安心して任せられるかどうかを判断できます。
特に、複数のジャンルのサイトを経験しているデザイナーは、目的に応じて柔軟にデザインを提案してくれる傾向があります。実績ページや紹介資料があれば、どのようなコンセプトで制作したのか、どのような成果を出しているのかも見ておくとよいでしょう。
チャットやWebミーティングでのコミュニケーションが円滑か
Webデザインの制作では、ヒアリング・確認・修正といったやり取りが何度も発生するため、コミュニケーションの取りやすさが欠かせません。チャットやWeb会議でスムーズにやり取りできる相手かどうかを、初期段階で見極めましょう。
質問への回答が丁寧か、説明がわかりやすいか、レスポンスが速いかといった点も確認しておくと、制作が進む中でのトラブルを防ぎやすくなります。信頼関係を築ける相手を選ぶことが、良い仕上がりにつながります。
サイトの公開予定日に間に合う制作スピードであるか
どんなに優れたデザインでも、納期に間に合わなければ意味がありません。依頼する前に、公開予定日やスケジュールの見通しを明確にしておきましょう。
制作会社なら、ディレクターがスケジュールを管理する場合が多いですが、フリーランスのデザイナーに依頼する場合は、他の案件との兼ね合いで納期が延びることもあります。最初の打ち合わせの段階で、どのくらいの期間でどの工程を進めるのか、ざっくりとでもスケジュールを共有しておくと安心です。
依頼する業界の経験や知識があるか
自社と同じ業界の制作経験があるデザイナーは、業界特有のデザイン要素や訴求ポイントを理解しています。たとえば、美容業界なら清潔感や柔らかさ、IT業界なら信頼性や先進性など、業界ごとに求められる表現があります。
過去に同業種のサイトを制作した経験があるかどうかを確認しておくと、企画段階から提案の質が高くなりやすいです。制作会社であれば、担当者が過去に手がけたプロジェクトを具体的に聞いてみるのも良いでしょう。
修正可能な回数や追加料金が明確か
見積もりを確認する際に見落としがちなのが、修正に関する条件です。多くのデザイナーや制作会社では、「◯回まで無料で修正可能」といったルールを設けています。それを超えた場合、追加料金が発生することがあるため、事前に明確にしておきましょう。
特に、デザイン完成後に構成変更を行う場合は、追加費用が大きくなるケースもあります。最初の段階で、どの範囲までを基本料金に含むのか、どの程度の修正が無料対応になるのかを確認しておきましょう。
Webデザイナーに外注する際の基本的な流れ

Webデザイナーへの外注では、目的の整理から、依頼範囲の決定、見積もり、制作、納品まで、複数のステップを踏んで進めていくのが一般的です。ここでは、初めて外注する人でもスムーズに進められるよう、基本的な流れをわかりやすく紹介します。
制作する目的・ゴールを決める
最初に、Webサイトを作る目的を明確にしましょう。「新規顧客を増やしたい」「採用ページを充実させたい」「ブランドイメージを刷新したい」など、ゴールを具体的に設定しておくことで、デザイナーも方向性をつかみやすくなります。
目的があいまいなまま進めてしまうと、デザインの修正が増えたり、納期が遅れたりする原因になることがあります。どのような成果を期待しているのかを、社内で共有しておきましょう。
どこまで社内で行い外注するのかを明確にする
Webサイト制作は、構成・デザイン・ライティング・撮影・コーディングなど、多くの工程から成り立っています。そのすべてを外注するのか、一部を社内で対応するのかをあらかじめ決めておきましょう。
たとえば「テキスト原稿は社内で作成し、デザインとコーディングのみ依頼する」「写真撮影だけ外部カメラマンに依頼する」など、役割分担をはっきりさせることで、作業の重複や認識のずれを防げます。
必要な素材や情報をまとめて整理しておく
依頼前に、Webサイトで使用する素材や情報をあらかじめ整理しておくと、制作がスムーズに進みます。会社概要やロゴデータ、掲載したい写真、原稿、参考サイトのURLなどをまとめて共有できる状態にしておくのが理想です。
素材がバラバラのままだと、制作が一時停止したり、修正が重なったりして納期に影響が出ることもあります。完成度の高いサイトを作るためにも、初期段階で情報をそろえておきましょう。
外注先を検討し相見積もりを取る
外注先を選ぶ際は、複数のWebデザイナーや制作会社に見積もりを依頼するのがおすすめです。金額だけでなく、提案内容やスケジュール感、対応の丁寧さなどを比較することで、自社に合ったWebデザイナーを見つけやすくなります。
相見積もりを取るときは、依頼条件を統一して伝えてください。同じ条件で比較しなければ、金額や作業範囲を正確に比べることが困難であるからです。提案内容の具体性や、質問への回答の速さも判断材料にするとよいでしょう。
Webデザイナーが作業・修正を行い納品する
契約が決まったら、いよいよ制作がスタートします。最初にデザイン案の提示があり、その後必要に応じて修正を重ねていくのが一般的な流れです。修正の回数や対応範囲は契約内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
デザインが確定したら、コーディングや最終チェックを経てサイトが完成します。納品後にデータの受け渡しや公開作業、ドメイン・サーバーの設定などが行われ、正式にWebサイトが公開されます。制作後も、アクセス分析や更新方法の相談などを通じて、継続的なサポートを受けられる場合もあります。
Webデザイナーに外注して業務負担軽減・質の高いサイトを作ろう
Webデザイナーへの外注は、単にデザインをお願いするだけではなく、企業のWeb戦略全体を強化する手段です。プロの手でデザイン性と使いやすさを両立したサイトを構築できるだけでなく、社内の作業負担を減らし、本来の業務に集中できる環境づくりにもつながります。
外注を上手に活用すれば、社内のリソースを効率的に使いながら、自社の魅力を最大限に引き出すWebサイトを制作できます。時間や手間をかけずに高品質な成果を得たい方は、ぜひ信頼できるWebデザイナーへの外注を検討してみてください。
一覧へ戻る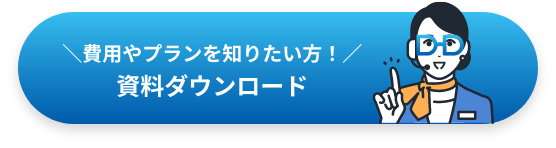 PAGE TOP
PAGE TOP